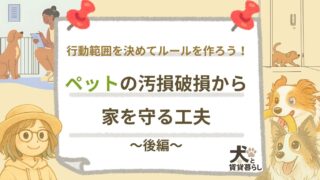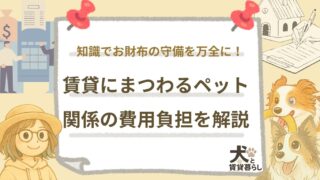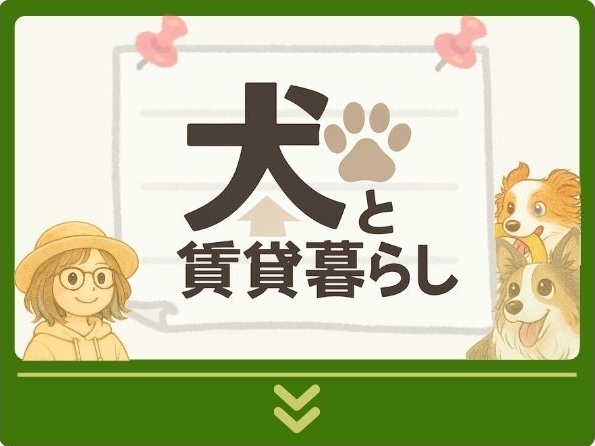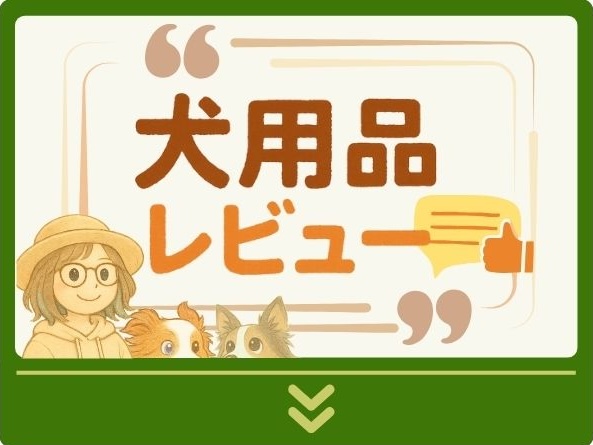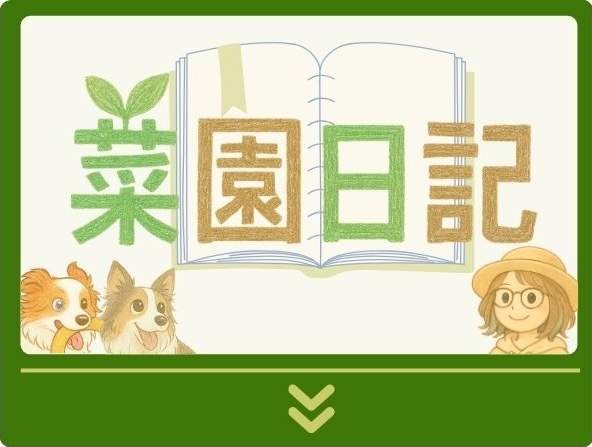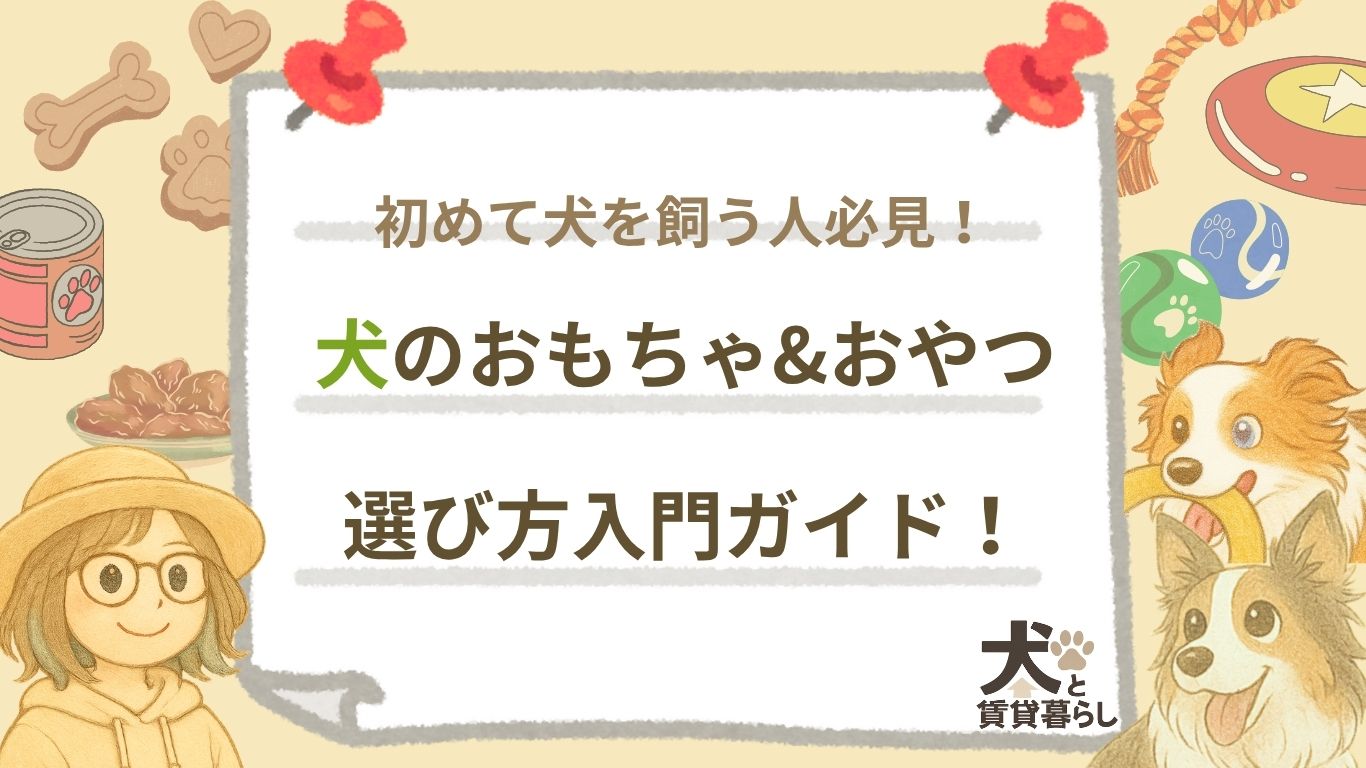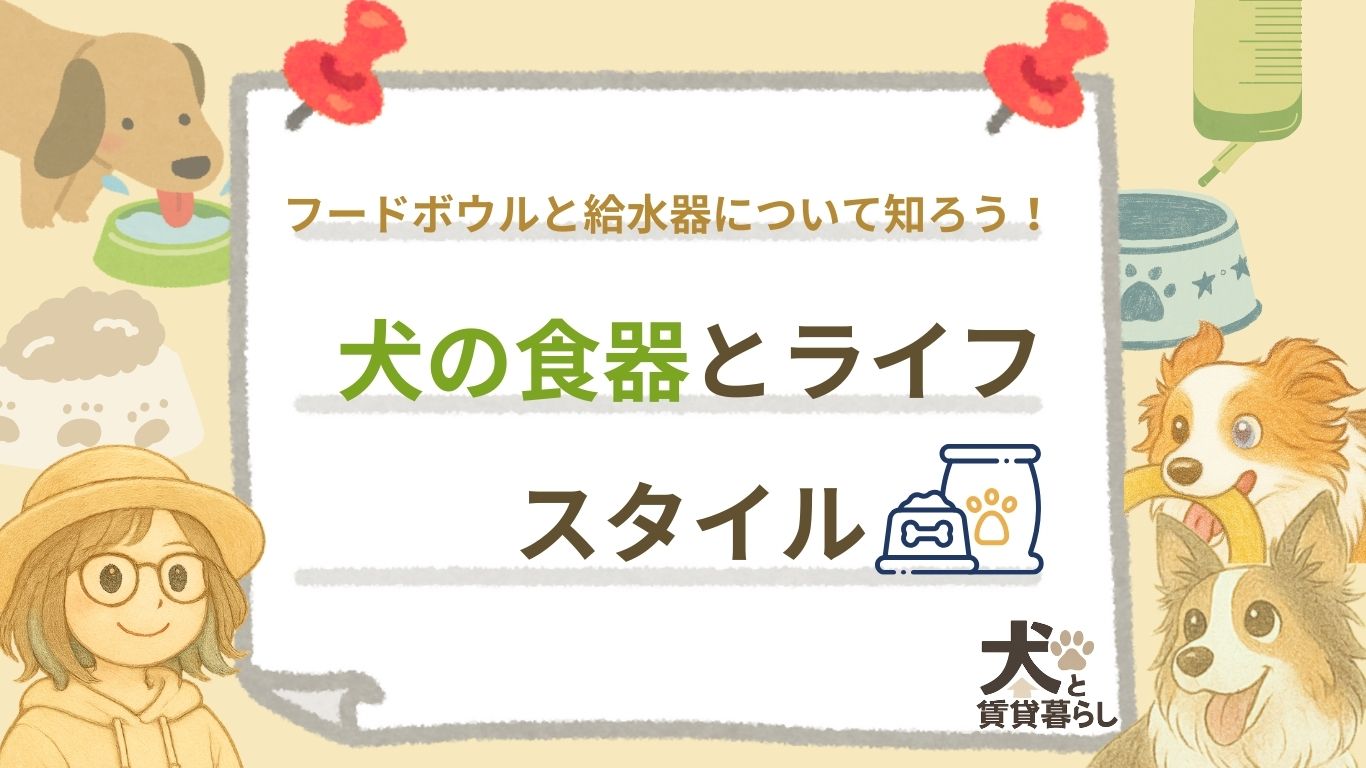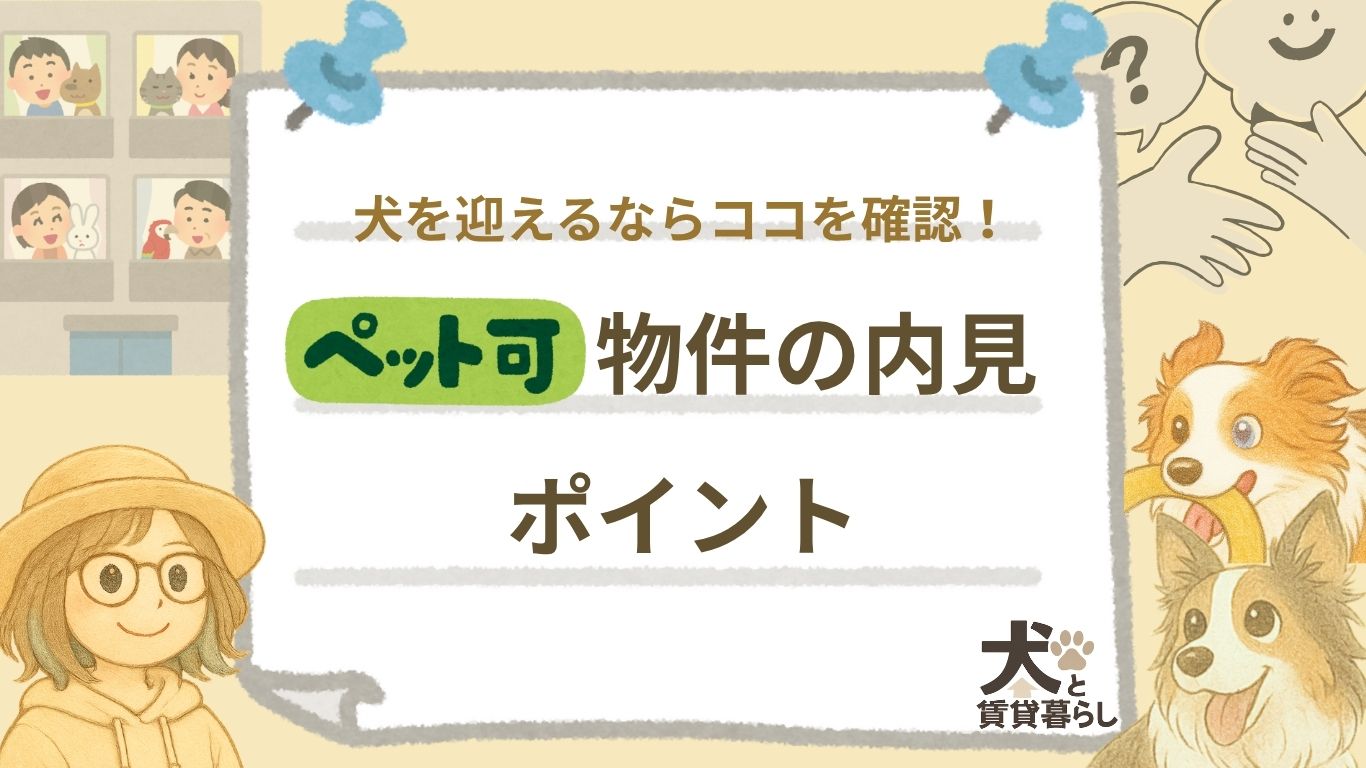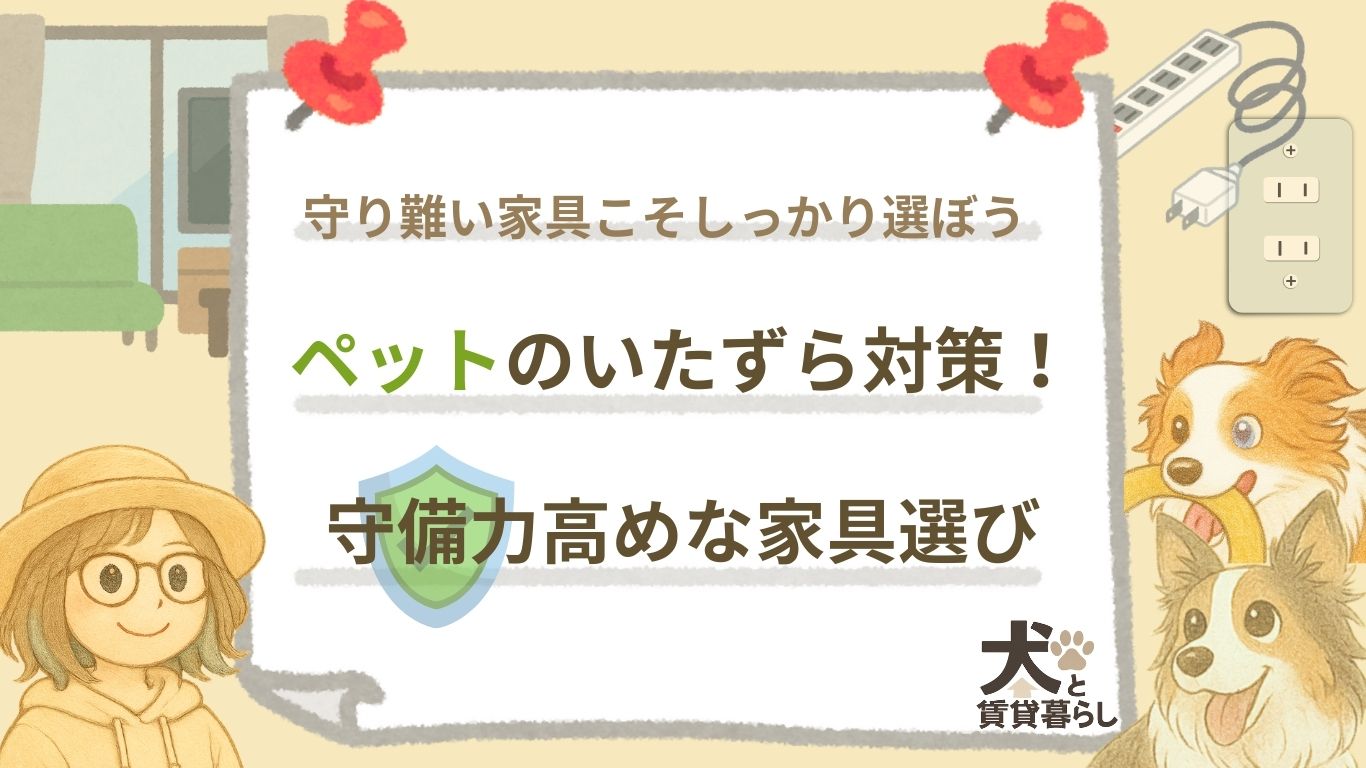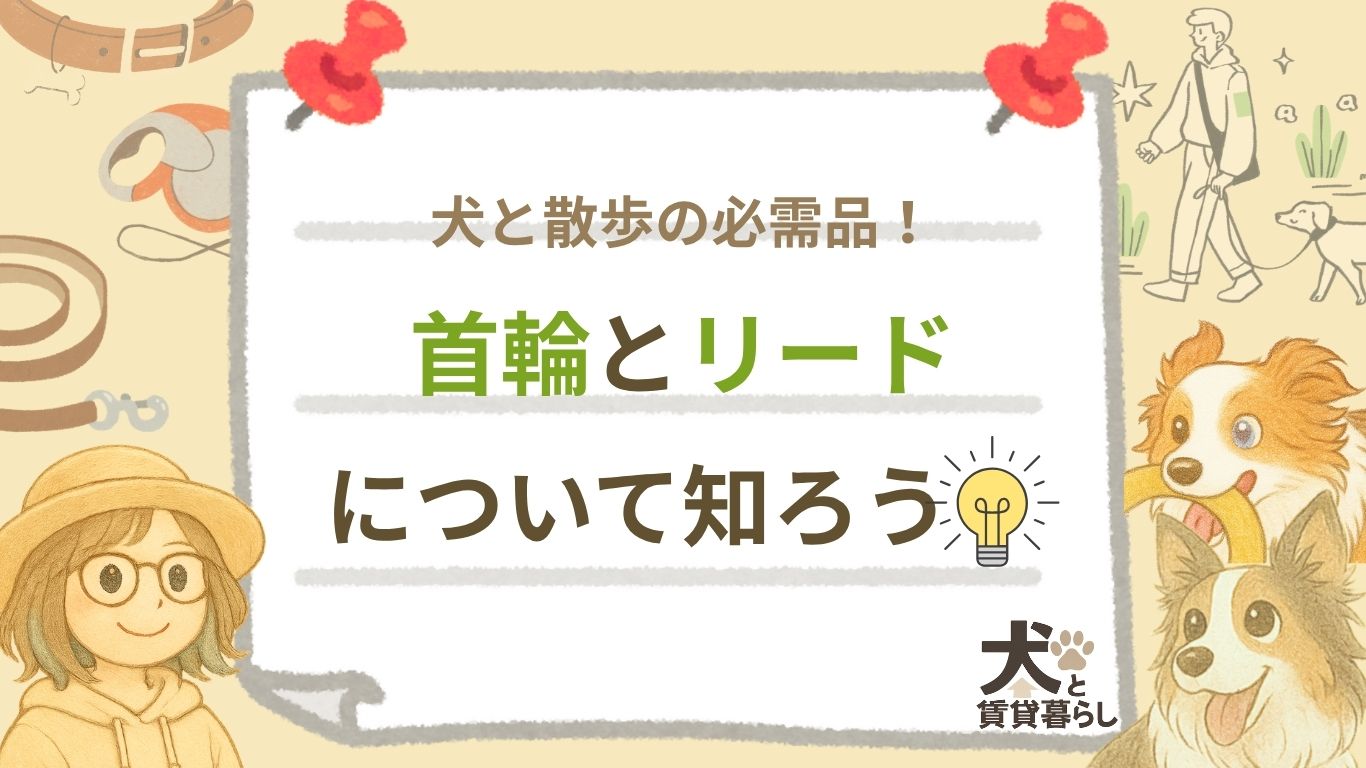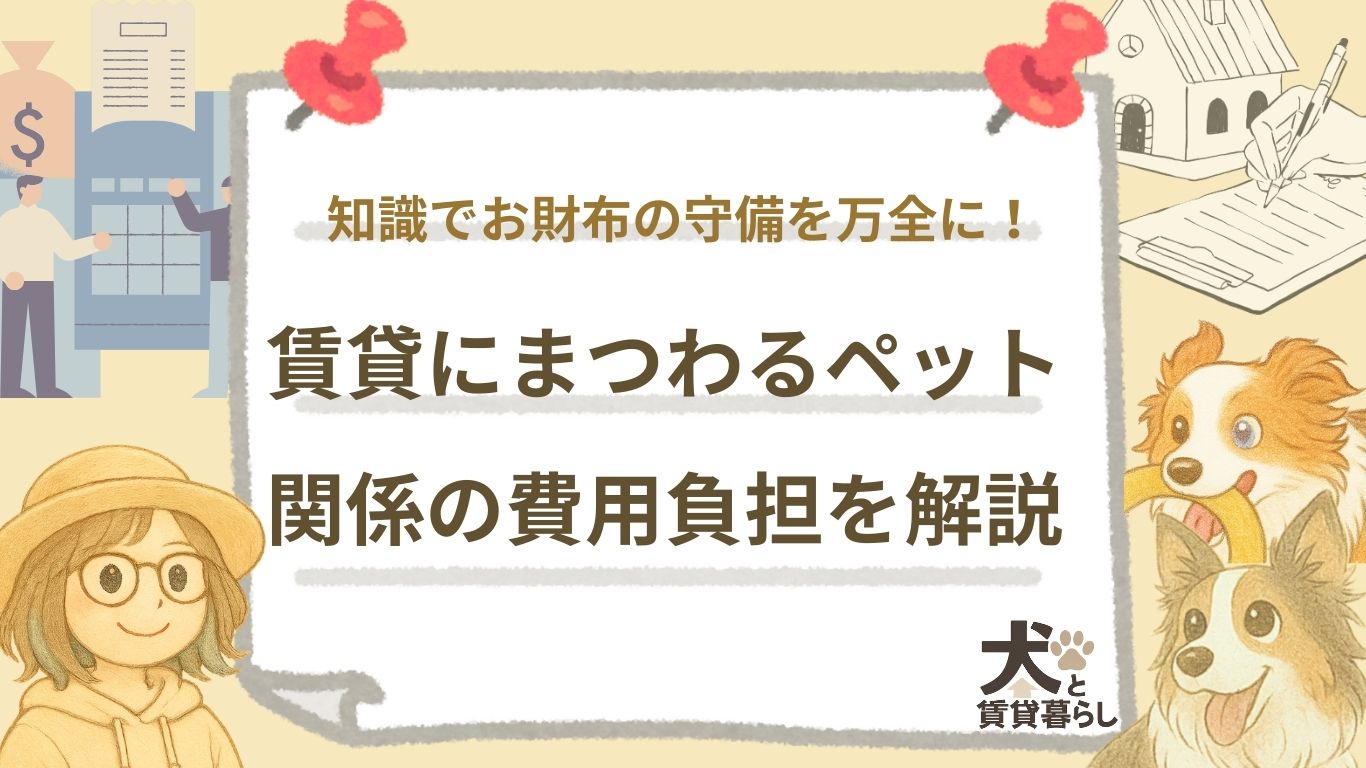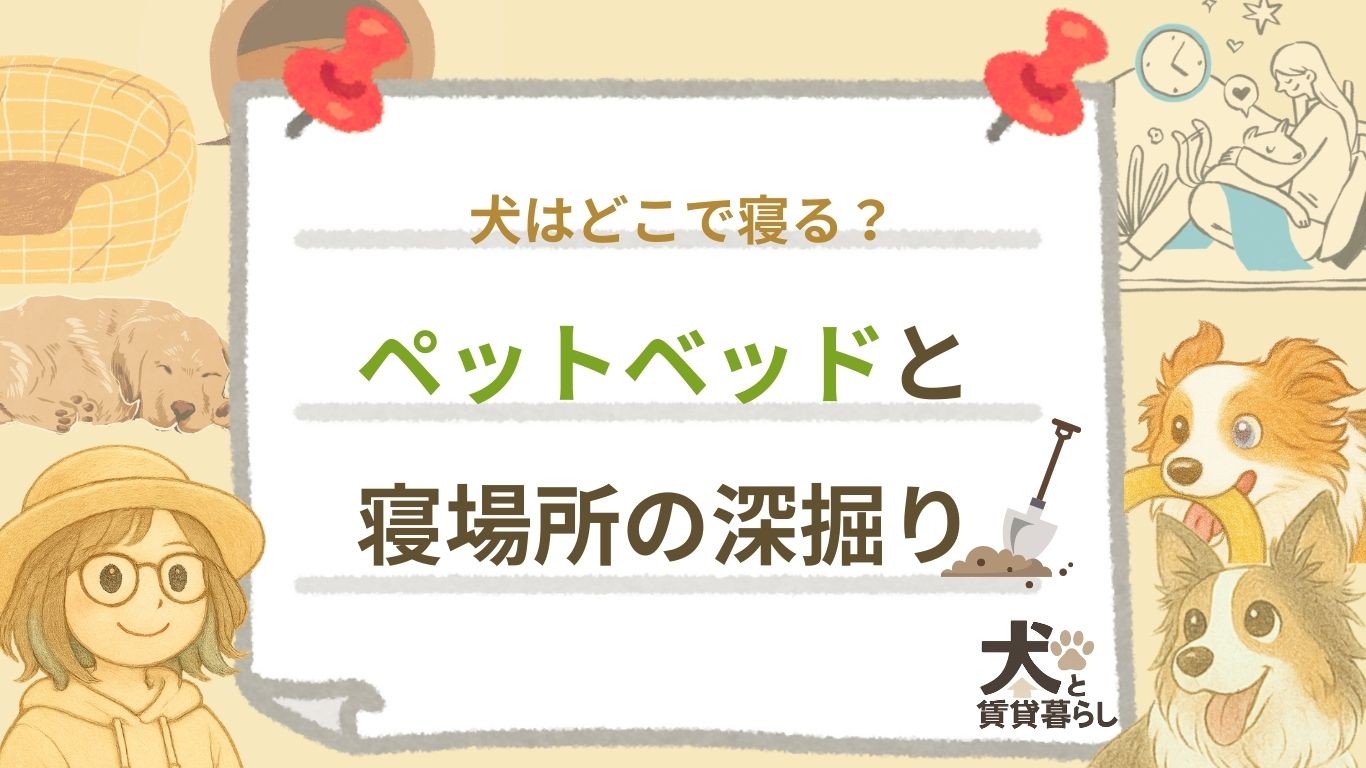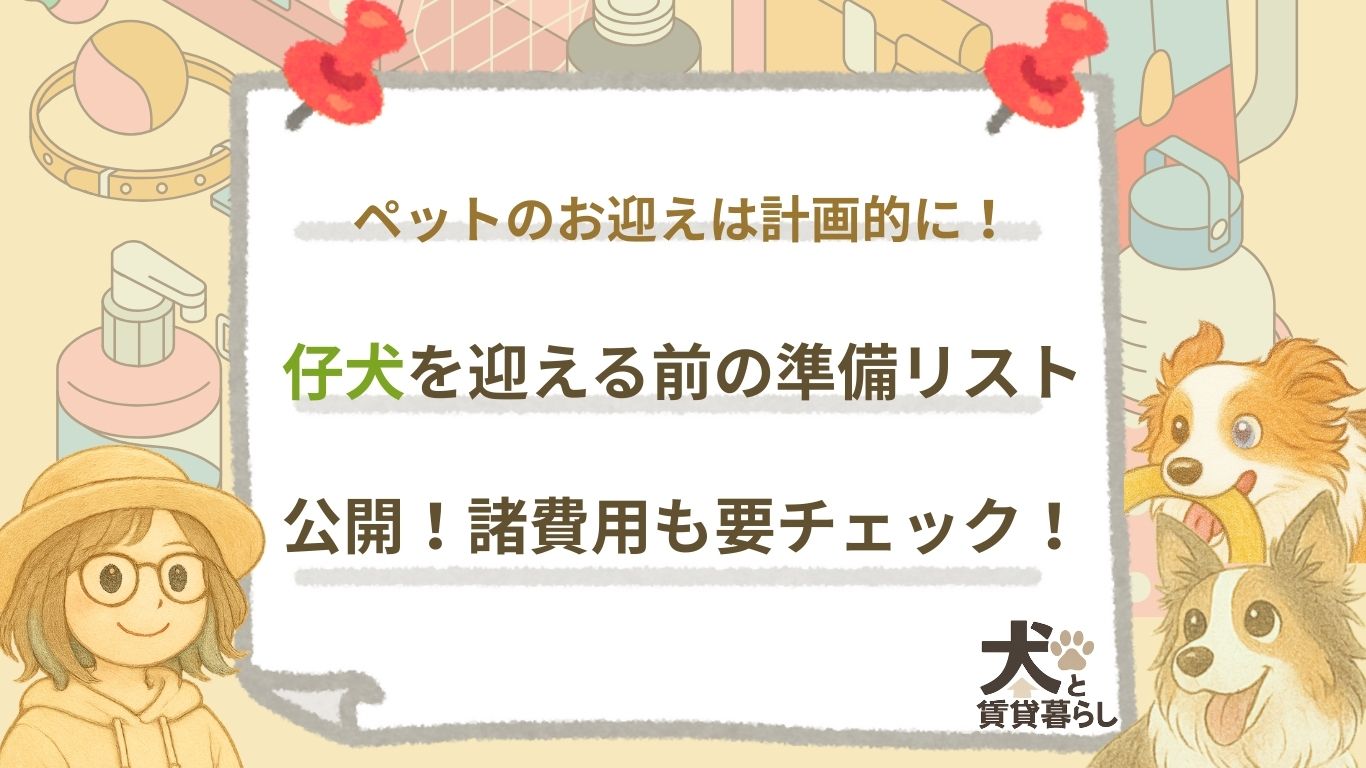【犬と賃貸暮らし】ペットの汚損破損から家を守る工夫〜前編〜
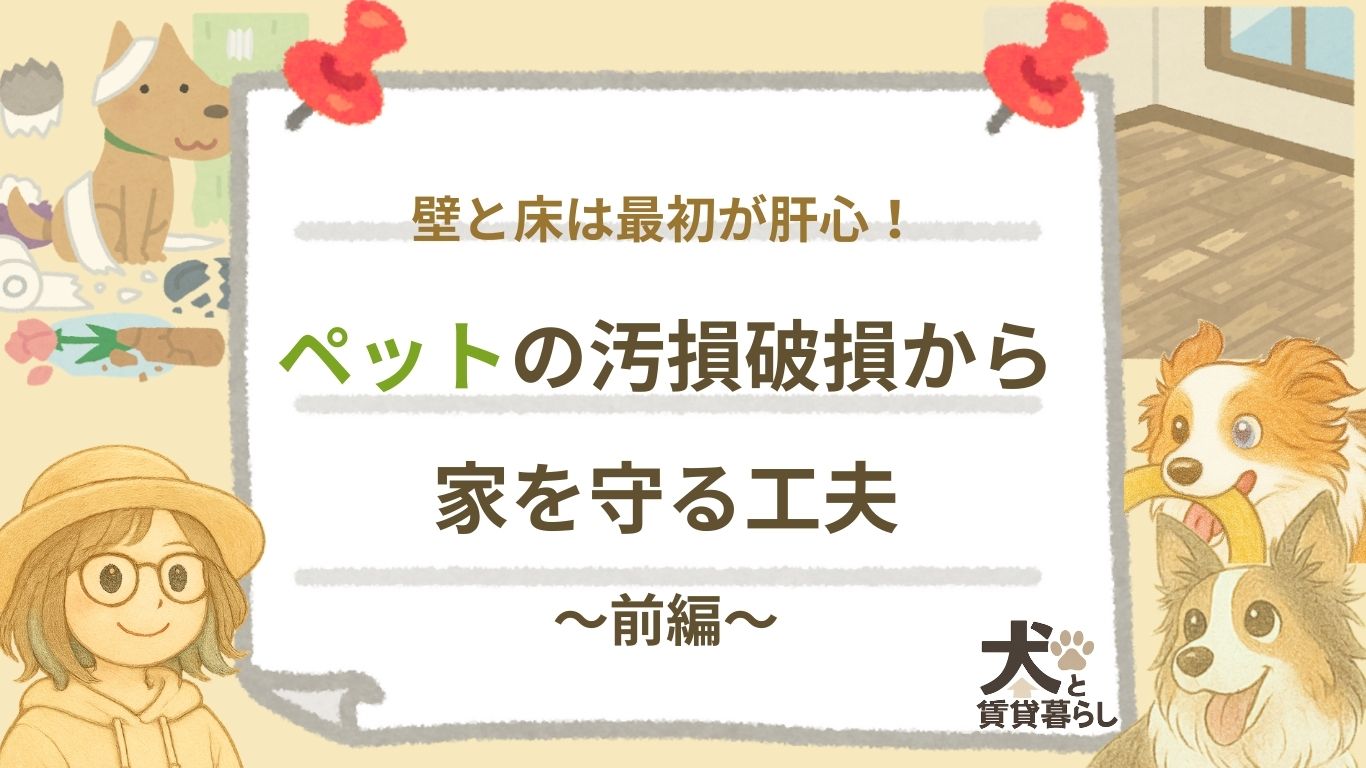
※このブログに掲載しているイラストは、すべてChatGPTで生成しています
こんにちは!すこやか管理者です。
ペット可能賃貸でペットをお迎えする前にはお家を守るひと工夫が必須!
今回のテーマは「犬と賃貸暮らし」第四弾「ペットの汚損破損から家を守る工夫」を紹介していきます。
前回、賃貸でペットを飼育する上でかかる費用(主に退去費用)について「ペットを飼っていないお家よりも退去時の原状回復の負担額が大きくなる可能性があるよ」というお話をしました。
入居前から退去に備えるの?とちょっと手間に思うかもしれませんが、原状回復は入居当初の状態に部屋を修繕することなので途中から始めるより、最初に対策しておくことがおすすめです。
本編では筆者が実際に「入居時にやっておいて良かった」/「こうしておけばもっと良かった」と思う汚損や破損の対策をお伝えします。
少し長くなるので、前編と後編の2回に分けてじっくり紹介を予定です。
それでは、ゆっくりしていってくださいね☕️
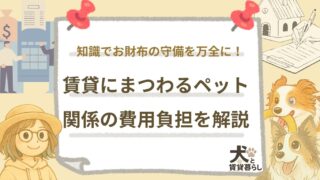
〜登場人物紹介〜

おもちゃ遊び大好きな7歳のボーダーコリーの男の子!最近少しずつシニア感が増してきている。

少しビビりだけどおてんばガールな5歳のボーダーコリー!遊び<食べ物でたまにゆっちのおやつを盗む。
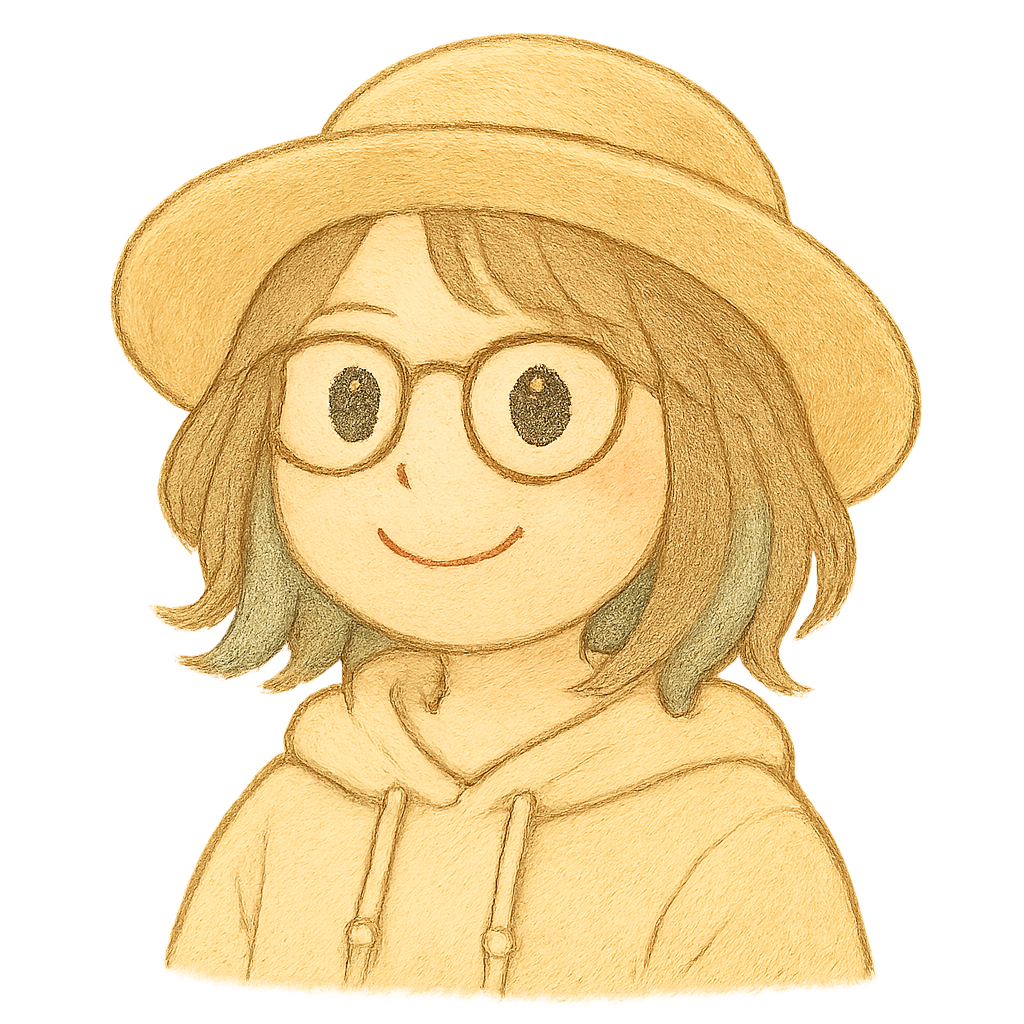
ブログ主でありゆっちとはっちの飼い主。犬飼歴は7年で普段は都内の企業で働くOL。最近プランター菜園をはじめた。
ペットを新居に連れてくる前の準備
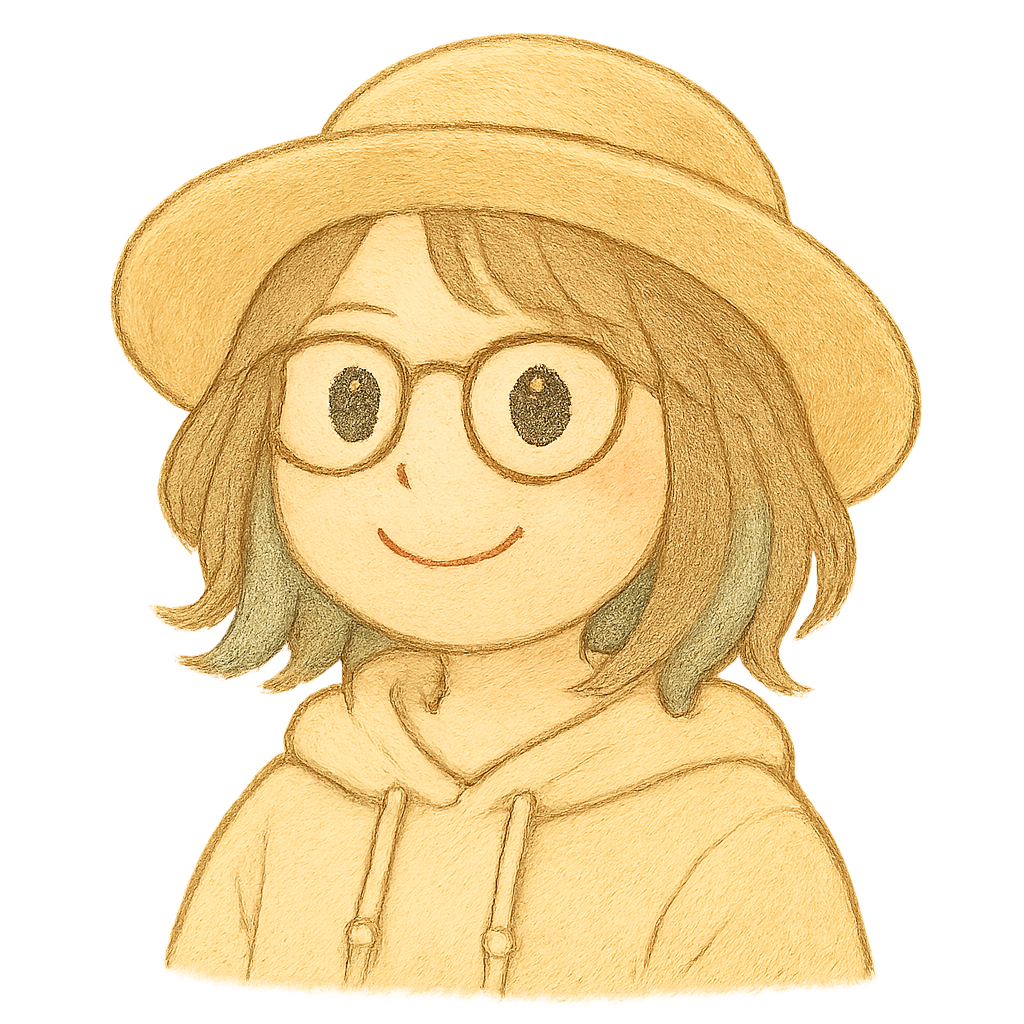
住むところが決まったら入居までにできることがいっぱいあります!
特にペットをお迎えするのであれば、退去時に綺麗な状態で部屋を返却するためにも汚損・破損に対する対策は必須です。

対策か〜。ちょっと手間だなぁ。
ここで頑張っておかないとペットの汚損や破損については退去費用の負担割合が通常と異なることと、火災保険の保証対象外になるから守る必要があるからがんばる💪
…でもさ、具体的にどんな対策すればいいの?
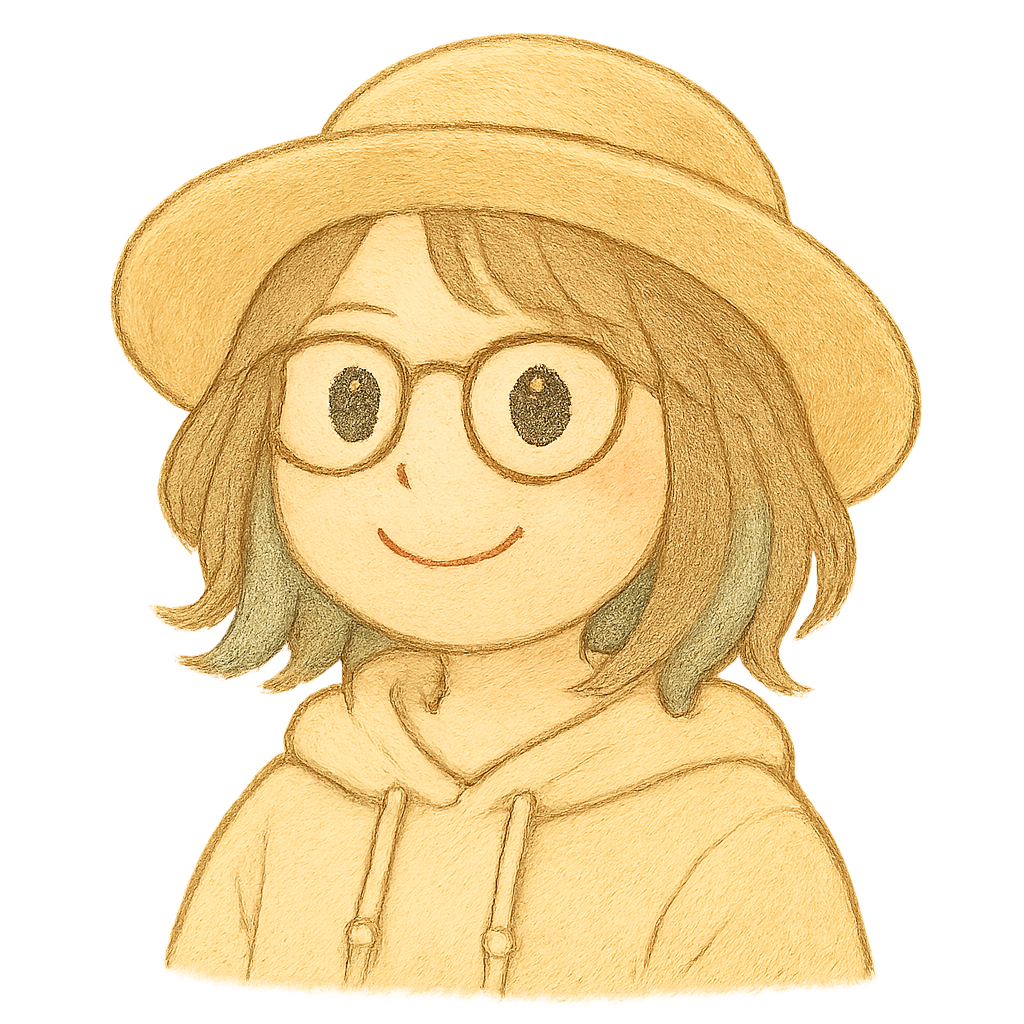
よしよし、じゃあ実際にやってよかった方法を紹介していきますね!
ペット関連の退去時の費用負担は前回の記事で詳細を記載していますが、ペットの汚損や破損についての原状回復の費用負担の割合は賃貸契約時の特約の内容によって変わります。
また、ペットの汚損や破損については「故意過失による損耗(日常的かつ十分に予測できる範囲の損害)」となるため火災保険の適用範囲外でした。
となると、入居時になるべく汚損や破損から守れるように準備を整えたほうが、後々退去費用に困ることが減りそうです。
そこで、犬を新居に迎え入れる前にいくつか済ませておくと役にたつ準備を紹介します!
お伝えする内容は15kg前後のボーダーコリー2頭に対して行っている準備なので必要に応じて使うものの種類はご自身でカスタマイズしてくださいね
- 階段、床にマットを敷く
- 壁に防汚、防傷シートを貼る
- 入ってほしくない部屋にはペットゲート設置
- 引き戸ならベビーロックをつける
- 庭に塀なし、生垣のみの場所にはネット設置
もちろんすでに一緒に暮らしている方にも今以上に傷や汚れが広がらないためにお勧めできる内容です。
ただ、先に犬を連れてきてしまうと爪で床に傷や壁に汚れがついてしまうなど、防御するには手遅れになりがちですので可能な限り犬を連れてくる前に実行してくださいね。
それではリストの内容を1つずつ見ていきましょう。
①階段、床にマットを敷く
物件によって床材はフローリング、絨毯、クッションフロアなど様々です。
どの床材でも犬が走る掘るでつく傷やトイレの失敗による汚れや痛みを防ぐためにはそれなりの防御は必要になるとは思いますが、ここでは筆者が実際に住んだことのあるフローリングとクッションフロアに絞って、防護用マットを紹介していきます。
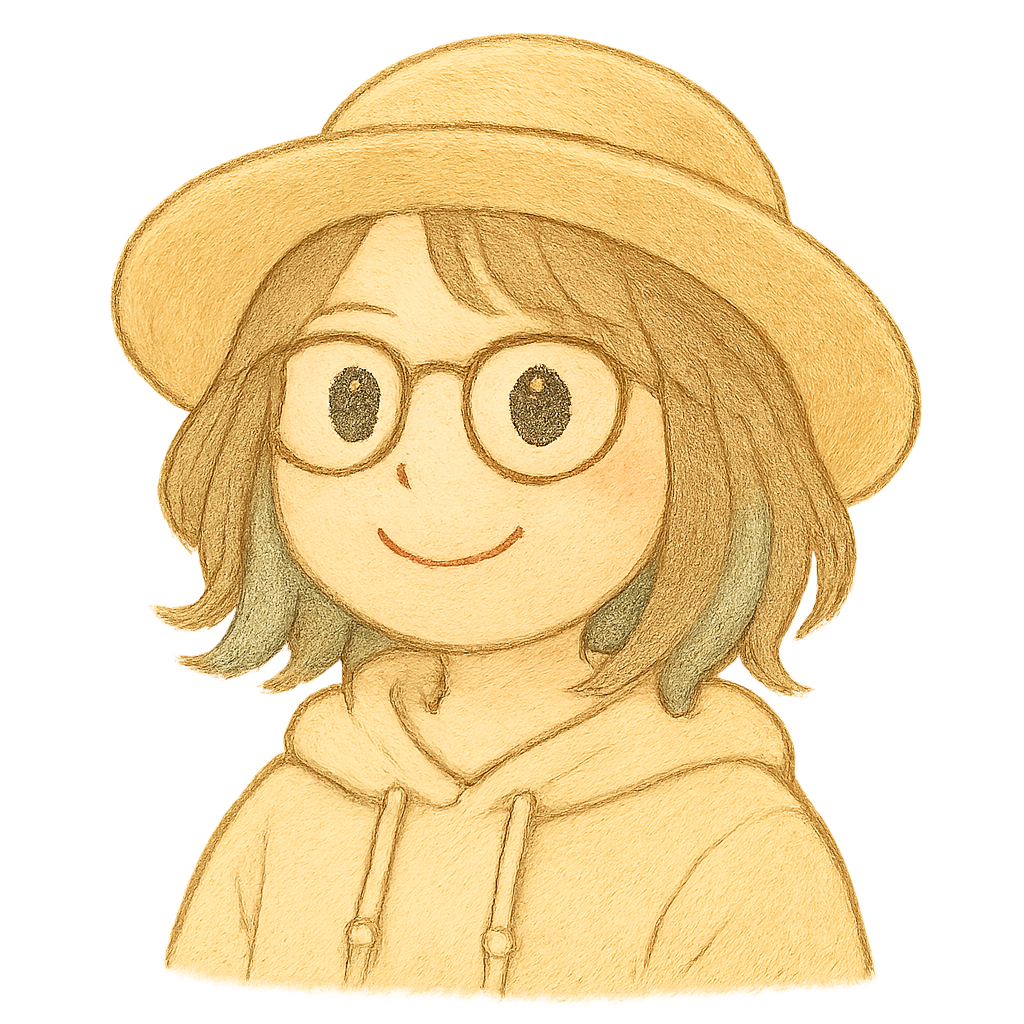
補足ですが、クッションフロアはフローリングなどベースとなる床材の上に敷く塩化ビニル系素材でできたクッション性のあるシートです。
マット選びの前にまずは各床材のメリットとデメリットを見ていきましょう。
フローリングのメリット・デメリット
フロアクッションのメリット・デメリット
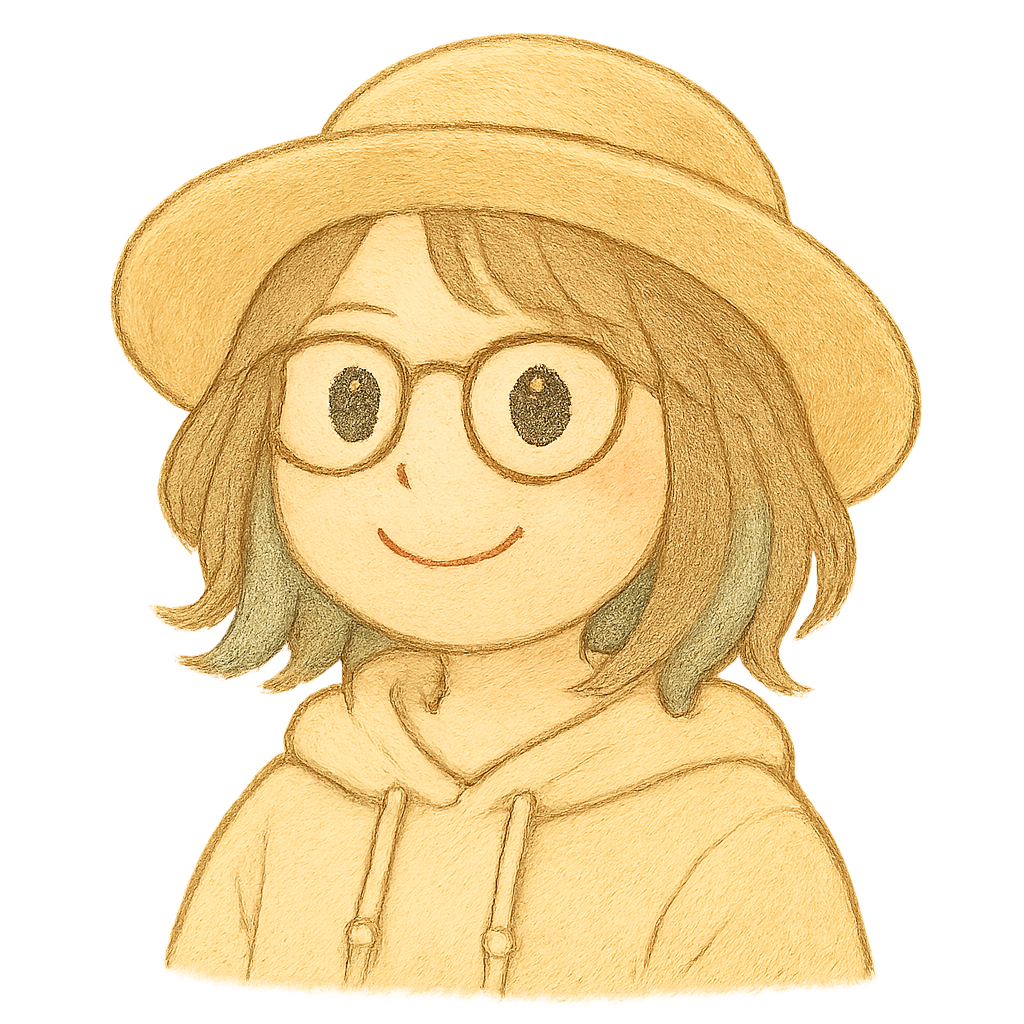
床材についてはどちらも一長一短。
フローリングは上からクッションフロアを敷くこともできます。
傷をつけないように住むのであればフローリングの上からクッションフロアを敷くが傷がつかず、水をこぼしてもそこまで気にしなくて済むので楽でした。
それぞれの床材について把握したところで、敷物を見ていきましょう!
おすすめできる敷物は「ラグ・カーペット」「タイルマット」「クッションフロア※フローリングの上に敷く場合」の3種類です。

ラグ・カーペット
・サイズが豊富で重さがあり滑り止め付きのものを購入すればずれにくい
・毛並みがリングタイプのものは犬の爪が吹っ飛ぶ可能性がある
・ふかふかで底冷えや足音をある程度防げる
・汚れると洗濯・乾燥が手間

タイルマット
・カラーバリエーション豊富
・手軽でカットできるタイプもあるので隙間なく敷ける
・水をこぼすと並べた隙間から水分が床に染みる場合がある
・激しく動くとズレる
・1枚単位で手軽に洗える

クッションフロア
※フローリングの上に敷く場合
・防水で水が染み込まない
・クッション性があるので滑りにくい
・クッションフロアの上からクッションフロアを重ね張りはできない
・色素沈着することがある
・破れると部分的な補修が難しい
・木目調、タイル調などデザインが豊富
個別に紹介していますが、実際に使用するときは用途に合わせて複数組み合わせて使用するのが良いと思います。
例えばフローリングの上にフロアクッションを敷き、寛ぐスペースには上からラグを敷く、階段や踊り場にはタイルカーペットを敷くなど。
敷く場所の広さや予算、犬たちのトレーニング状況に合わせて購入してください。
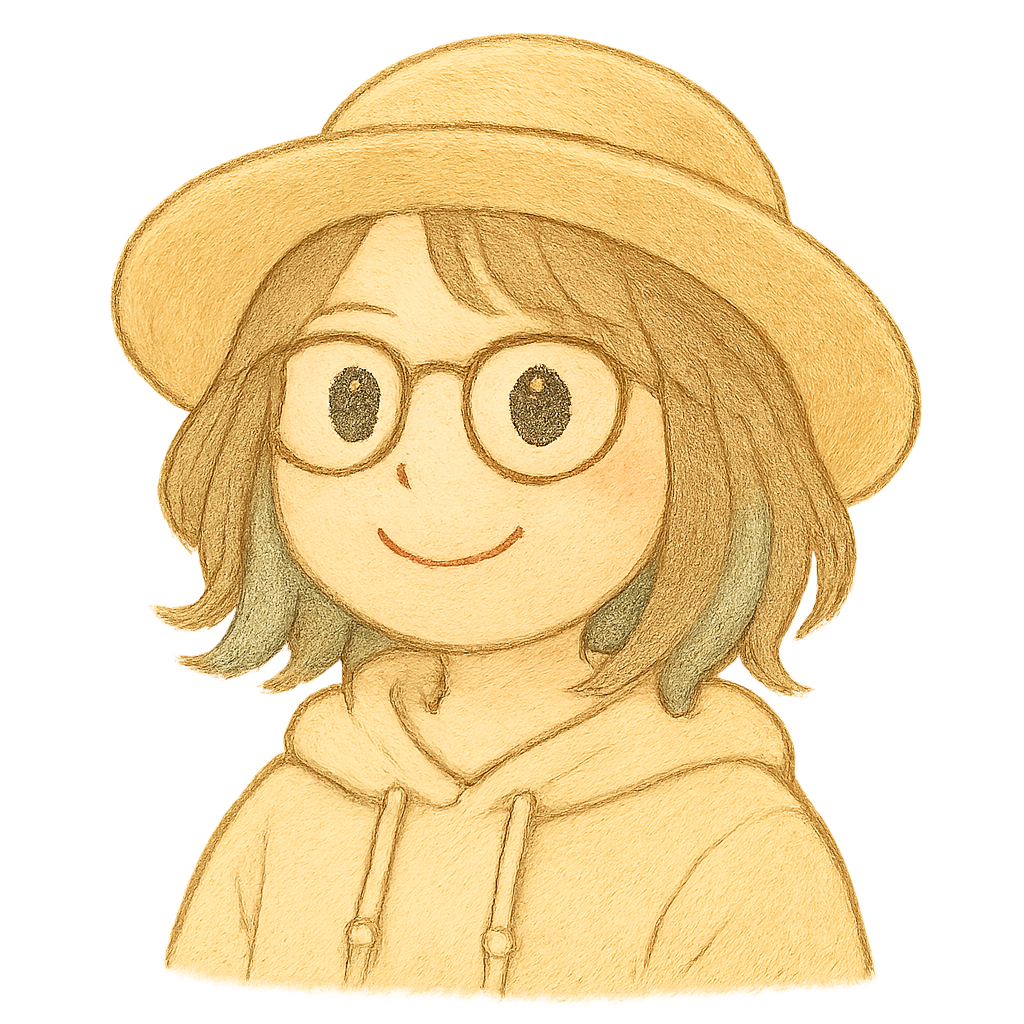
仔犬期は特に粗相をしてしまうことが多いので、メンテナンスに手間がかからないことは重要です。

おトイレの回数も多いけど、排泄物を踏んで気が付かないでいろんなところを歩いたりするから、タイルマットにして部分的に洗うか、クッションフロアとか防水性のシートがお掃除しやすいよ!

まあ、今は洗濯までしなくてもちょっと飲み物こぼしちゃったとか、子犬の粗相くらいならサクッと掃除できる、リンサークリーナーなんて便利なものもあるよね。
掃除機みたいな音がしてぼくは苦手だけど。
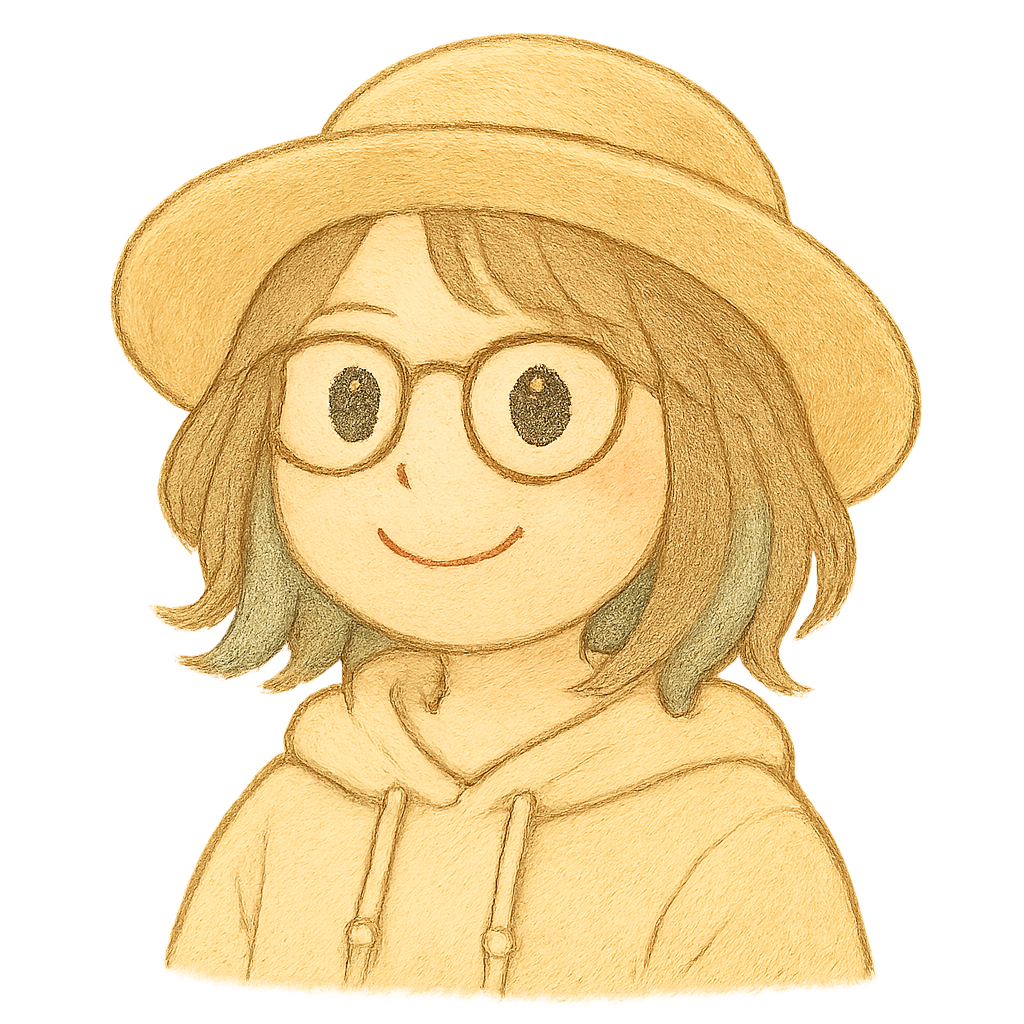
リンサークリーナーの存在を知った時はこんな便利なものあるのか!って衝撃だったね。
まあ、掃除関連の話はまた今度ゆっくりしましょう。
②壁に防汚・防傷シートを貼る

壁はそんなに汚れないよね?すぐ拭けば大体落ちるし、こんなに広いんだから対策するだけ大変だよー
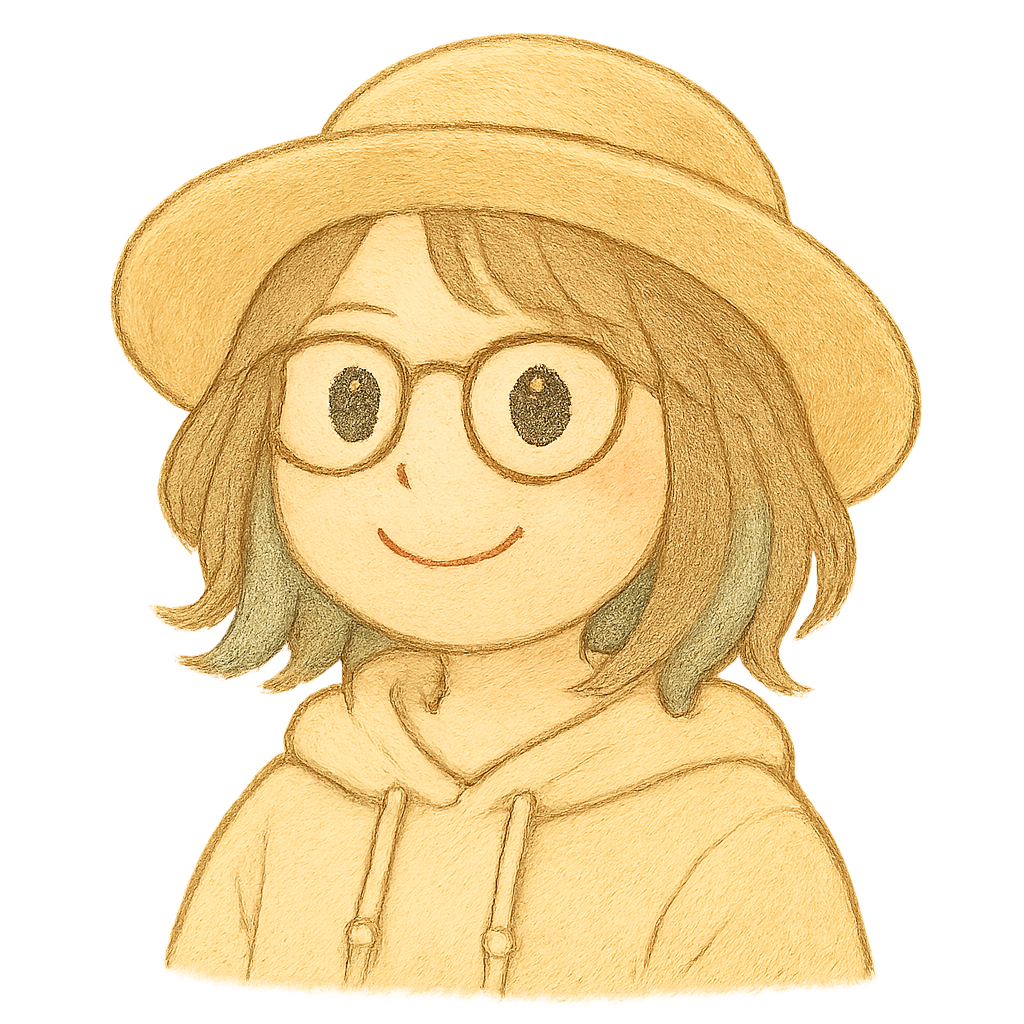
まあまあ、そう言わずにさ。
気づかない汚れから守るだけでなく、傷から守ったり、最終的にはお財布を守ることにも繋がるから最初だけでも頑張ろう!
犬と暮らしていくと、壁をかじってしまった、粗相をして壁紙に匂いや色がついてしまったなど仔犬の頃はどうしようもないトラブルがつきものです。
もちろん成犬になってからも少しめくれてた壁紙を好奇心で引っ張って剥がしてしまったり、片足を上げて排泄したら壁に飛んでしまったということもあります。
このようなトラブルを想定して少なくとも下半分、犬の出入りが多い部屋の壁には防汚・防傷シートを貼っておくことをお勧めします。
キッチン周りの壁紙(油染みや調味料の跳ね返り防止)
犬のトイレ周辺(おしっこの跳ね返り防止)
犬と過ごしている部屋の壁下半分(犬の体についた汚れすりつけ防止)
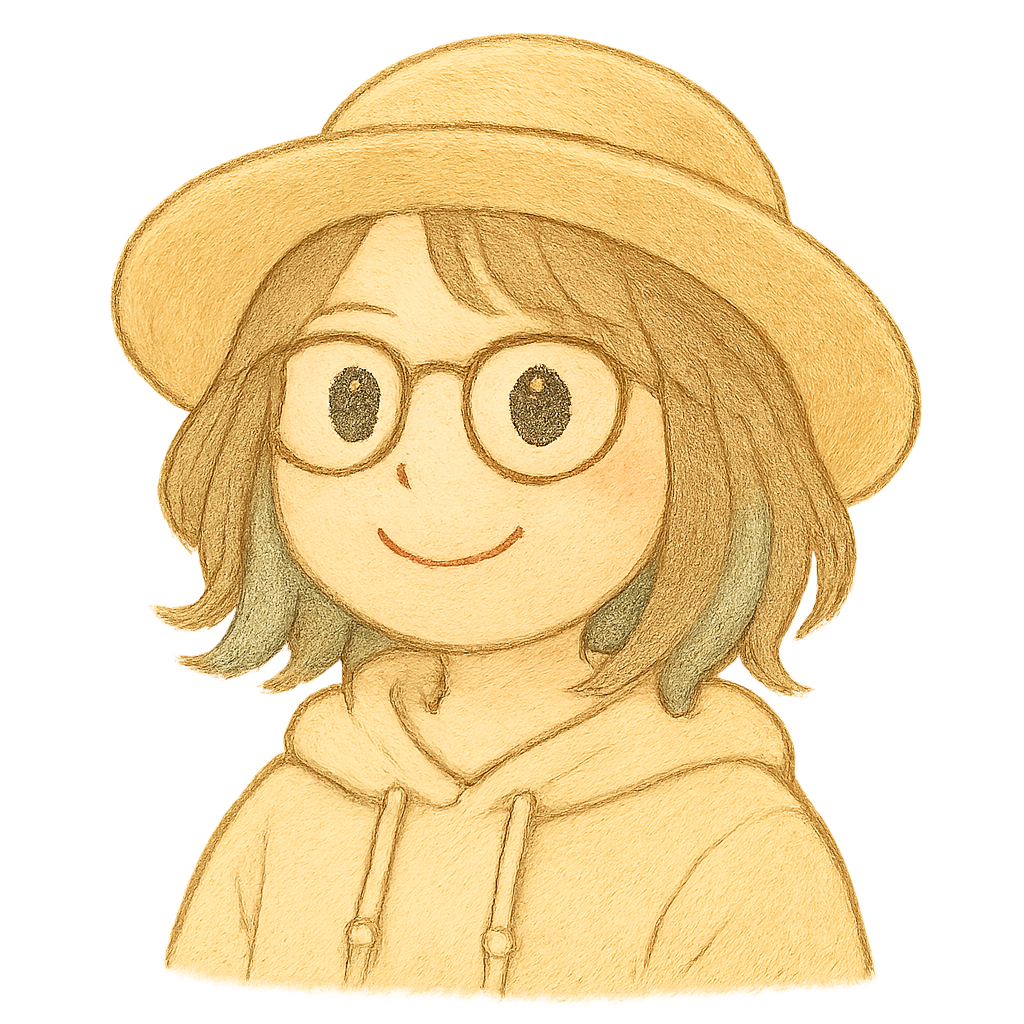
どの防傷・防汚シートが良いのかはレビュー記事を探してみたり、口コミを確認すると良いと思います。
個人的にお勧めなのは猫の引っ掻き傷防止シートです。
傷に強く、透明なものもあるので部屋の印象を変えずに壁を守ることができます。
そのほかの壁を守る手段としてはプラ段を貼る方法もあります。
厚みがあり、簡単に破くことができないので、
特定の場所を集中的に狙われるのであればプラ段(プラスチック素材でできたダンボール)で覆って保護する方法が役立ちます。
プラ段を使う場合は誤飲を防ぐためにも「大きめにカットして両端を家具で押さえておく」が良いと思います。
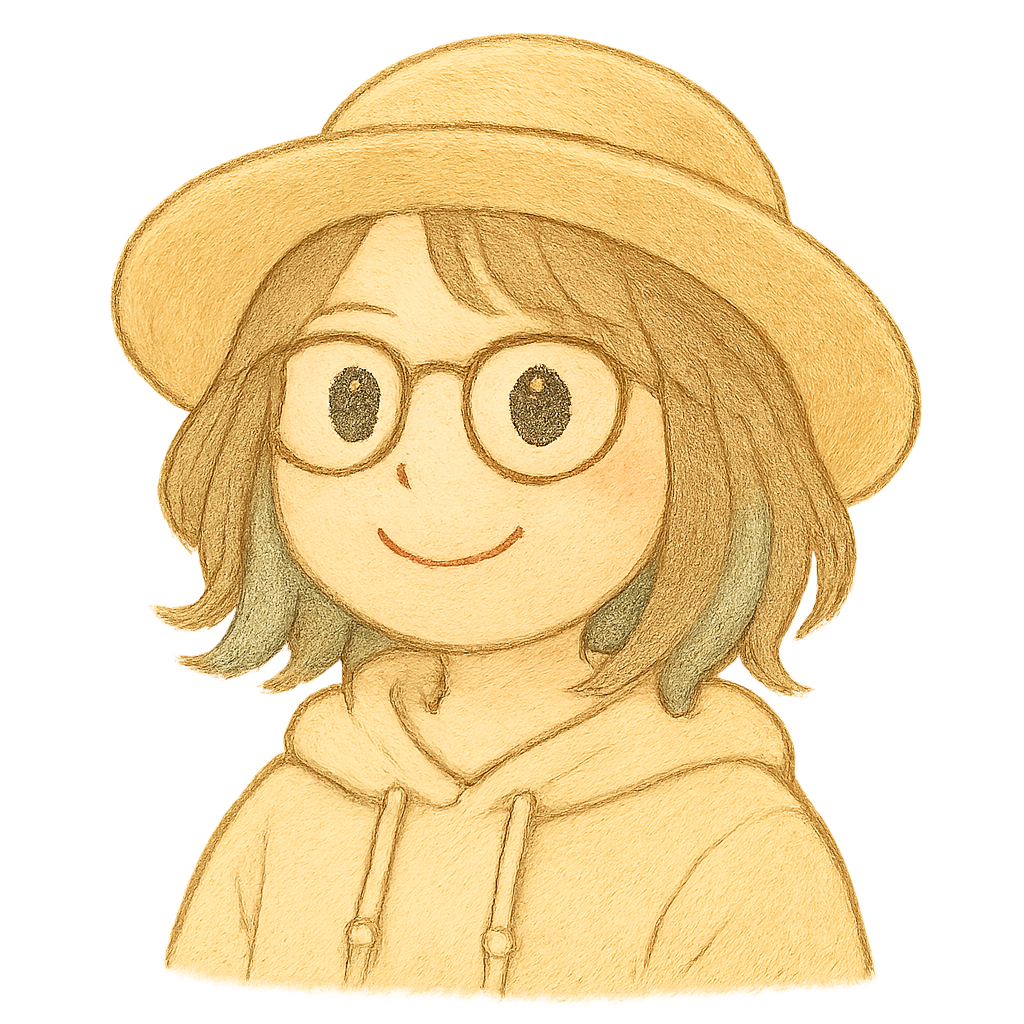
プラ段はあくまで壁にたどり着くまでの一時的な防壁です。過信せず、壁にたどり着く前に愛犬を止めましょう。
壁紙の修繕費用のあれこれ
あまり身構えないように少しだけ修繕費の話をしておきます。
壁は何もせずとも、長く住んでいれば日焼けで変色しますし、ノリが弱くなって捲れることもあります。
このような生活している上で時間の経過とともに自然発生する劣化を経年劣化といい、新しく壁紙を貼ってから年数とともに壁紙の価値自体がなくなっていきます。
ペットが傷をつけてしまった場合は原則として借主負担となりますが、
国土交通省のガイドラインに基づき「経年劣化分」が考慮されます。
壁紙の耐用年数は6年とされていて、住んでいる年数によって借主の負担が減るので、万が一ペットが壁紙を傷つけてしまっても長く住んでいれば全額負担にはならない可能性が高いです。
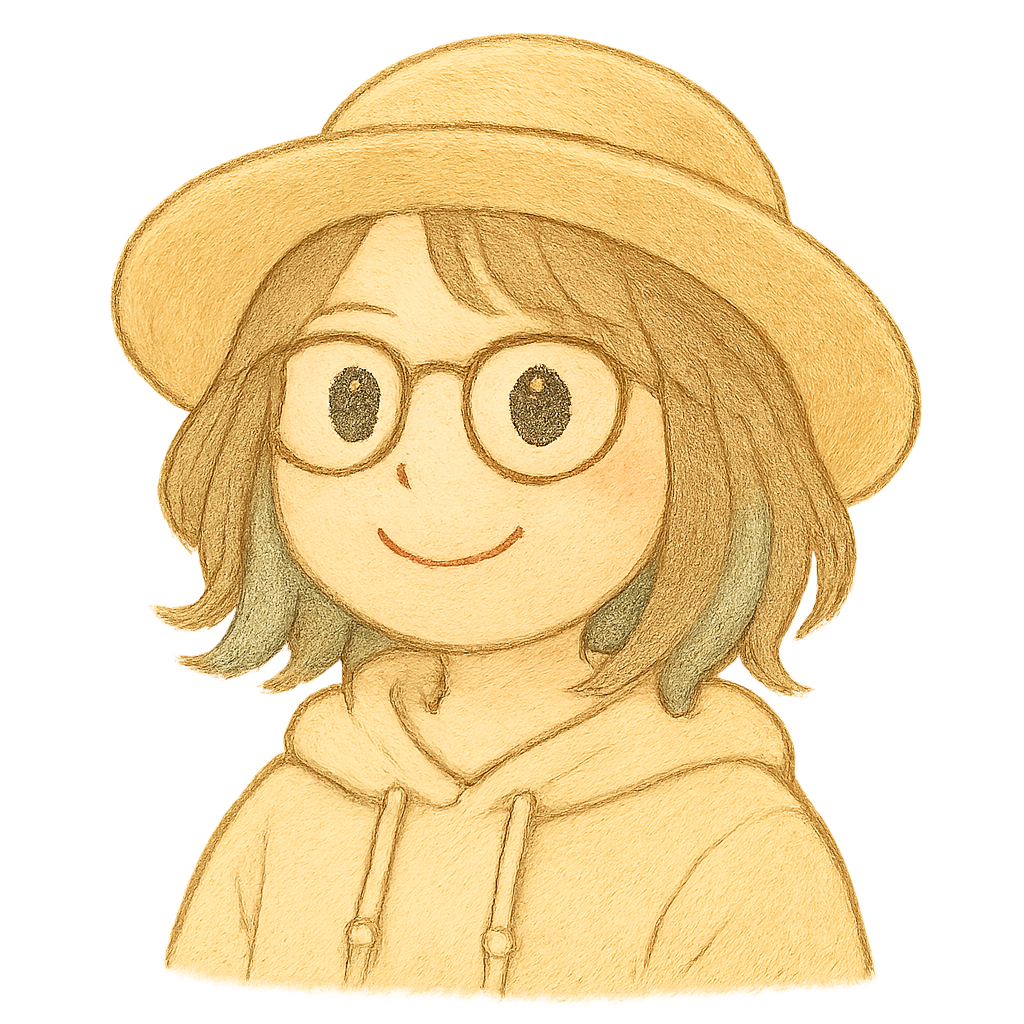
経年劣化に関わらずペットの汚損破損の負担割合は特約で決められている場合もあるので契約内容は把握しておきましょう。
とはいえ、借りたものは綺麗に返すのがスジですし。
今後も賃貸に暮らしたいと考えているなら、この人になら貸しても良いと思ってもらえる使い方をしましょう。
ここまでのまとめ
・床や階段には床材にあったマット敷いて傷を防御
・フローリング →「クッションフロア」「ラグ・カーベット」「タイルマット」
・クッションフロア →「ラグ・カーペット」「タイルマット」
・壁には防汚防傷シートで排泄物の飛び跳ねや爪傷、かじり傷を防御
・おすすめ → 「猫の引っ掻き傷防止シート」
・さらに強固にするには「プラ段」
・シートは必ず貼って剥がせるタイプにする
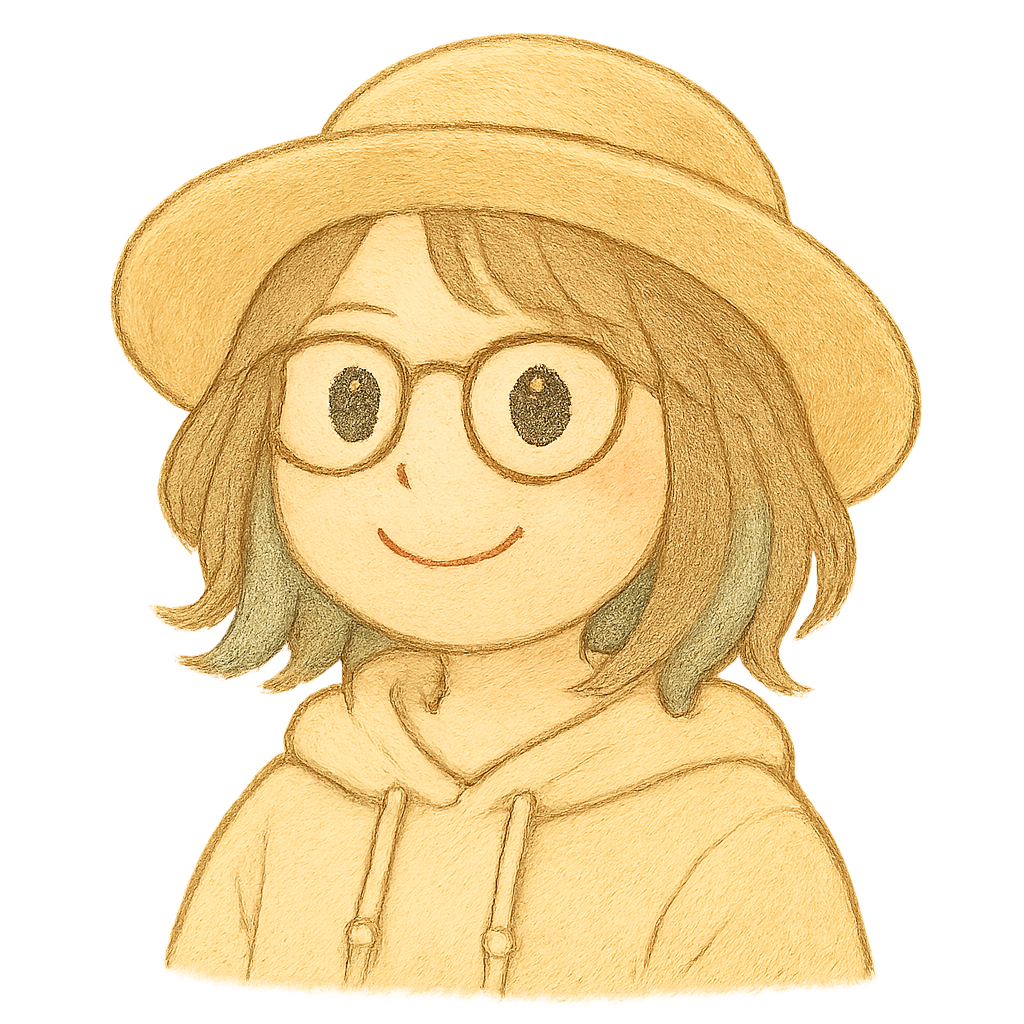
前編はここまで!後編では「ペットゲート」「ベビーロック」「脱走防止ネット」についての用途を紹介しますので、ご興味をある方はぜひ読んでくれると嬉しいです!

後編も守るための工夫を紹介するからぜひ読んでね!